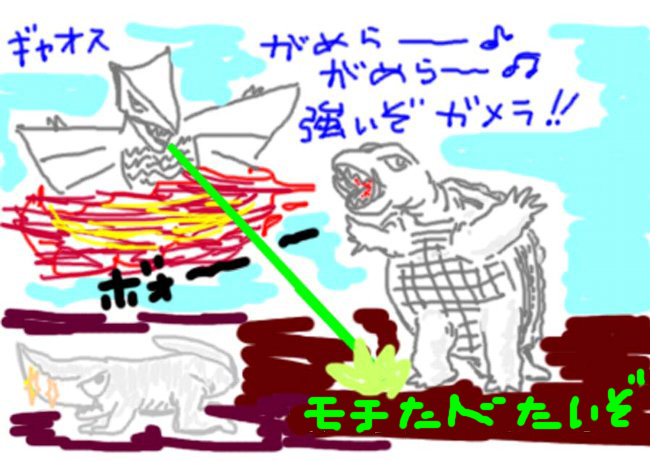■「 樽樽源 上新粉講座 」
ええとね ( ^ ^)b まず一番最初に「 上新粉 」という物は餅米ではなく「 うるち米 」を原材料に作りだしている物だってことをお伝えしたいです。
え?! ∩( ̄ω ̄;∩)
・・・ってことは手にした餅が上新粉100%製であれば「 餅 」という商品名であっても「 餅米 」ってのは入ってないってことですか?
おお太郎くん (^ 。 ^ ) キミは早速良いところに気がつきましたね。
( ※誰が太郎やねん 勝手に名前決め付けんといて:笑 )
でも餅米が使われていないから イコール 「 餅じゃないのか? 」とか短絡的に考えちゃ駄目だぞ☆
その辺りのことは下の文面を読みこんで学習するといい。
レッツ STUDY ♪
「 餅米の製粉 」と 「 うるち米の製粉 」ではその製造過程までもが異なる。
↑ このことが理解できていないと両者の特質が理解できないから シッカリ 学習しておこう☆
まず「 上新粉 」の製造の工程はこう ρ(^∀^ )
①「 うるち米 」を精白します。
②次に精白した「 うるち米 」を水に浸ける。これは「 うるち米 」が熱に弱いからだって。
③これを粉砕したのちに乾燥作業を行う。
④これで「 うるち米 」の米粉が完成。これを「 新粉 」って言うのだそうな。
⑤あとはこれを篩い(ふるい)にかけて粒子の細かさを選別してゆきます。
⑥粒子の「 粗い 」⇒「 細かい 」の並び順に「 並新粉 」、「 上新粉 」、「 上用粉 」と名前が付けられるっす。
どうだい? (*^ ^)b 「 上新粉 」の精製過程イメージが掴めたかな?
ちなみにこれに対して「 餅米 」を製粉した物の名称は「 白玉粉 」と呼ばれています。
白玉粉を作るときは「 うるち米 」とは違い水に浸したうえでの製粉作業は要らない。
うりゃ うりゃ☆ っと餅米を砕いてゆき細かくしてゆくんだそうですよ。
でも このウンチク話・・・ 実際に作業をみたわけでは無いので間違っていたら御免なさい m(_ _)m
上新粉は、柏餅、お団子、焼せんべい、草餅などに使用されているんだけれど、上の工程紹介でも話したように精白したうえで製粉工程を辿り誕生する特質上、作られた菓子が真っ白でコシが強くなる上、食感としては シコッ♪ と噛み切れる印象に仕上がるんだってさ。
そんな「 歯ごたえの良さ 」が前面に出やすいのが上新粉ね。
また この特徴に対して「 ねばりの強さ 」では餅米がわに軍配があがるといった違いがあるとのことです。
ん・・・・ でも ちゃきさん 精白してから粉にするから上新粉で作る製品が 真っ白さに磨きがかかる のは理解ができたよ。
だけど「 ねばり強さ 」の部分で「 うるち米 」と「 餅米 」で違いが出てくるのは何故なんだい。
そこんとこが一番の食感の違いに結びつく所でしょ 大事な部分じゃん 違いますか σ( ̄ o  ̄ ) あん?
(;つ゜□゜)つ ))))))) ドキッ!
キミ達 なかなか す す するどいね・・・・。
ええと・・・ 確かねぇ 栄養学のお勉強で習ったウンチクを動因するとですね。
デンプン含有量の割合の違いで ねばり気 ってのに違いが出たはずです。
ええとぉ・・・・ ちょっと調べてきます f(^ 。 ^;)
暫しお時間を・・・・ それまでは下の歌とイメージ画像を見聴きして待っててね。
もっち 餅 噛めよぉぉ~♪ 亀さんよぉ~ (^▽^ ☆
世界のうちでお前ほどぉ~ 歩みのノロイ者は無いっとぉ~♪
どうしって そんなに(餅)旨いのかぁ~~♪
( 急いでいるのにノロイならタクシー乗れば良いのにね ぐはは )
んで歌に登場した 亀 ちゃんイメージです ρ(o^∇^o) 描いてみました
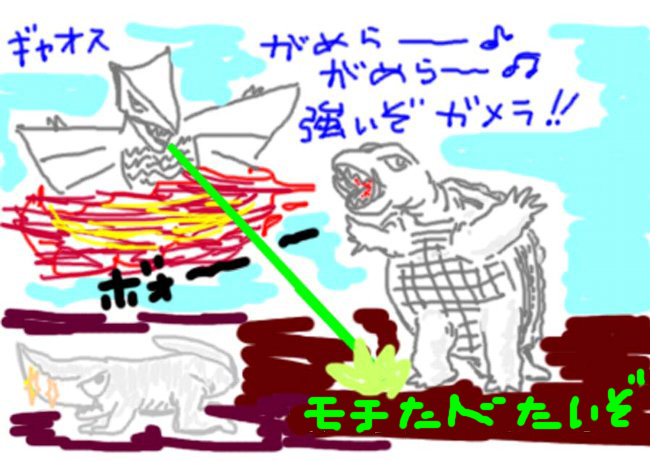
・・・・というわけで時間も稼げたために無事に調べ物も終了。
ええ・・・こほん (ーp ー ) それではいきますね。
まず やはり両者はデンプン質の含有量が違っていました。
餅米は「 アミロペクチン 」というデンプン質100%で出来ているそうです。
対する うるち米の方はといいますと「 アミロペクチン 」が80%ほどと「 アミロース 」が残り20%ほどを占めるんだって。
んでもってこの「 アミロース 」という物が経時変化で硬さを顕著にしてゆく作用があるんだって。
「 硬さ 」は程良い歯切れの良さを産み出すのに好都合でしょ☆
だから上新粉を上手に使いこなせば シコッ♪ と噛み切れる食感を演出するのに効果抜群ってことになるんだ。
対する餅米オンリー物はあの独特の みょ~~ん♪ って伸びまくる感じの粘り強さを呈することになる。
この差が両者の最大の食感差を演出しているってわけです d(^▽^*)
ふぅ・・・ ε-(;ーωーA やれやれちゃんとレポート出来て良かった。
読者の皆さんも ここまでくればもうお分かりのことでしょう。
上新粉と餅米粉は 作り手がどの食感を狙ってくるかによって使用する場面が違う だけってことがさ。
どちらも美味しい「 お餅 」を産み出す原材料に使われて不思議は無いってことが理解できたよね。
以上が今回お届けする「 樽樽源 上新粉講座 」でした。
どう? 色々判ったかな?
ようはこういうこと♪
ヽ(o^∇^o) 『 色々な食感のお餅を楽しんで行ってちょ☆ 』
 
ちなみに ここツルヤさんの作る「 草もち 」は 絶品です☆
特に販売時期が限定されている『 草しんこ 』なんてのはもう ヨモギの香りとか凄いんだからぁ~♪
キミ達はきっと『 餅を食べて感動する 』ってのが そうそう信じられないだろうね (^~^@)
オイラはツルヤ餅菓子舗さんの『 草しんこ 』を初めて口にしたとき あまりの美味しさの衝撃に倒れるかと思ったほどだかんな(笑)
いや でも冗談抜きにその味の良さには心の底から感動しました。
このヨモギなんだけど 天然物をお店の人達がわざわざ自分で採りにゆくのだそうですよ。
新芽のうちは深い色合いが出づらいのでこれを避け、ある程度成長したヨモギを選び手にしてくるのだそうです。
採取する時期によって味や風味もかわるのでしょうし、尚且つ餅に練りこむ際の量の多さを特徴としているツルヤさんのこと きっと「 量 」自体の確保にも相当の努力をなさっているのだろうなぁ・・・と容易に想像できますよね。
こういった事情から販売時期を限定することになっても それは「 自慢の美味しさ 」を守る上では仕方がないことに違いありません。
こういった努力や拘り感が ツルヤさんの餅を手にした人の心を動かすんだと思うんだ。
そんな凄い餅が小樽にはあるんですよぉ~( 自信満々 )
添加物の類を一切使わず 中に仕込む餡まで全てが
自家製で仕上げてゆく「 小樽逸品 」の味
ここの草餅は以前に土産の品として札幌暮らしの友人へと持参したことがありました。
彼も目ん玉を丸くしてその味の良さに驚いてたもん♪
小樽 w(◎ー◎;)w すげぇぇ~!!たじたじ・・・。
彼はその週の休日を利用して早速小樽入りし、目当ての御餅達を買い求めにやってきていたくらいですよ。
ぐはは してやったり☆☆☆ (^ ^)v ぶいっ!
ツルヤ餅菓子舗さんは決して表通りの目立つ場所にある店じゃない。
間違いなく「 探し出して訪ねる場所 」なはずさ。
それだけの労を供してでも訪ねる価値があるよ
・・・っというわけであえて命令口調で言わせて貰おう。
『一度は食べてみろ☆\(^▽^ )♪』と。
この日のチャキさん 無事に目当てであった2種類の草餅を両方手にいれることが出来て大そうご満悦です。
早速歩いていける場所にある花園グリーンロードで腰を下ろし ムシャ ムシャ と頬張っていましたよ。
旨いんだな これが (*^v^*) ウマウマで至福の時っすね☆

傍らの花壇には小さな花が咲いていた。
僕はこの花の名前は知らない・・・。
でも風にゆれる花の姿が心地よいことは知っています。
手には美味しい餅 目の前には花が咲く心地よさ。
先に登場した御餅達の画像と合わせて、のんびり気ままに過ごしていることが少しでも伝わってくれれば嬉しいです。
休日って「 山盛りに色々な場所を訪ねまくる使いかた 」もあれば、「 ほとんど何もせずに身体や心を休める 」ために使うことも出来るはず。
小樽の街やそこで営業するお店、公園に咲く花の姿などはそのどちらにも応えてくれると思っていますよ。
今回の僕のように目当ての餅屋さん一軒を訪ね、あとは近所の公園で気ままに過ごすのも良し。
ツルヤさんとシノギを削る実力をもった餅屋さんらもあわせて巡るも良しです。
キミ達はどんな使い方で「 小樽の餅 」を楽しみますか? ヽ(o^∇^o)
■最後は補足の説明として
今回紹介した「 草しんこ 」 なんだけど先にも少し触れたようにヨモギが採れる時期( ※6月くらいから10月くらいまでだと教えられてます )にリリースされるのでどうしても販売時期が限定されるんだ。
「 草しんこ 」が目当てで訪ねるのならば その時期には気をつけるんだよ。
勿論、「 草しんこ 」以外のお餅たちも美味しいのだからこれに限らず食べてみたいって人ならば時期を問わずで足を運んでみるといい。
地元では人気のあるお店だし午前中が勝負だと思います。
さぁ~てキミのお目当てなお餅は来店時まで残っているかなぁ~。
遠方の人ならば出発時間にはくれぐれご注意を♪
それでは本日のGOOD-LIFEもこの辺で。
またねん ( ^▽^)ノ ばいばい♪
小樽観光「樽樽源」トップページ > 小樽観光情報一覧 > ツルヤ餅菓子舗その2
|